第六話 牙城クスコ(3)
トゥパク・アマルの天幕では、彼を中心に円陣を描くようにして、側近たちが先刻の体勢のまま座っていたが、先ほどの面々に加え、そこには先刻は見られなかった一人の若いインカ族の青年の姿があった。
それは、アンドレスの神学校時代からの朋友、かのロレンソであった。
ロレンソはトゥパク・アマルの前に恭しく跪き、「どうぞ私にクスコへの使者としての任をお授けください」と、申し出ているところであった。
そう言ってから、決意を秘めた力強い眼差しで、トゥパク・アマルをじっと見据える。
その傍では、かのアンドレスが非常に強く案ずる色を滲ませた眼差しで、極めて危険な任務を申し出た友を制しに、それこそ今にも飛び出さぬばかりの勢いで身を乗り出していた。
トゥパク・アマルは、アンドレスと同年齢の、その勇敢な目前の若者に包みこむような静かな視線を送りながら、しかし、やはり考え深げに目を細める。
そこへ「恐れながら」と、ビルカパサが、トゥパク・アマルとロレンソの後ろに控えるように跪いた。
マルセラも、ビルカパサの少し後方に恭しく跪く。
ビルカパサは、「トゥパク・アマル様、ロレンソ殿、横からの申し出、誠に失礼をご容赦ください」と深く礼を払った後、「何卒、その使者としての役目、このマルセラにお授けください」と申し出た。
マルセラも深く礼を払い、それから、「どうぞ、そのお役目、この私にお任せください!」と、ゆるぎない決意を秘めた澄んだ瞳でトゥパク・アマルを真っ直ぐに見た。
側近一同も、ロレンソも、皆、驚いたようにそちらを振り返る。
なお、この時まで、マルセラとロレンソの間には全く面識はなかったため、同年代の若者がアンドレス以外にも身近にいたことに、互いの目はいっそう惹きつけられたはずである。
一方、アンドレスは「マルセラ!」と小さく叫ぶと、先ほどから揺れの止まらぬその澄んだ瞳をいっそう揺らしながら、いけない!そのような危険なことは…――と、思わず言葉に出そうになる。
トゥパク・アマルもまた、驚きを隠せぬ眼差しで、ビルカパサを、そして、マルセラを交互に見ながら、暫し、言葉を呑んでいる。
そのようなトゥパク・アマルに改めて礼を払い、ビルカパサが毅然とした口調で言う。
「さすがのモスコーソ殿も、公衆の注目する中、女人に危害を加えることはありますまい。
マルセラには、インカ貴族としての作法も授けてきております。
トゥパク・アマル様の使者として、決して不足無きよう振舞うこともできましょう」
トゥパク・アマルは、しかし、といった色をまだ滲ませながら、ビルカパサからゆっくりとマルセラに視線を動かす。
マルセラは、トゥパク・アマルの視線を受けて改めて姿勢をただし、とても恭しく礼を払った。
「マルセラ、そなたの勇気、深くこの身に染みたぞ」
トゥパク・アマルの誠意溢れる声音に、ハッと顔を上げたマルセラの瞳の中で、トゥパク・アマルは優しい眼差しで頷いた。
「しかし、この任務は非常な危険を伴う。
クスコは今や恐慌状態にあり、皆、ひどく気が立っておろう。
そのような中、使者とて、わたしの代理の者であれば、クスコの面々は憎悪の念から理性を失い、何をしてくるかわからぬのだ」
その深く案じ、包み込むようなトゥパク・アマルの真摯な眼差しを受け、マルセラの心に感極まるものが湧き起こる。
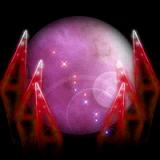
マルセラはもはや揺れる瞳を隠さず、しかし、きっぱりとした声で言う。
「トゥパク・アマル様、そのように敵方の気が立っている時だからこそ、厳(いかめ)しい殿方(とのがた)が出向かれるよりも、女の私が行った方がよいのだと存じます。
私とて、かつてのインカ帝国の都を血で染めたくはないのです。
この命、トゥパク・アマル様のために、そして、インカのために役立つのであれば、決して惜しくはありませぬ」
そう言って、そのビルカパサ似の凛々しくも澄み切った瞳で、しっかりとトゥパク・アマルの目を貫くように見つめた。
側近一同も、そして、ロレンソも、健気にも勇敢なマルセラの姿に胸の熱くなるのを感じながら、思わず息を呑む。
トゥパク・アマルもまた、その目を細め、静かな眼差しで、しかし、その目元に熱を帯びた光を宿して、じっとマルセラを見つめた。
そして、ついに、ゆっくりと頷く。
「わかった。
それでは、マルセラ、わたしの使者として、そなたをクスコに遣わそう」
トゥパク・アマルの言葉に、マルセラもビルカパサも深々と礼を払う。
その場にいた者たちも、二人の方に深く礼を払った眼差しで見つめる。
しかし、アンドレスと、そして、またロレンソにも、その瞳の中には、驚愕と激しく案じる色がまだ強く残っている。
そしてまた、表面に出さぬトゥパク・アマルの瞳の奥にも、微かに揺れるものがある。
彼は静かな声で続けた。
「そなたには、クスコで最も権力をもっておられるモスコーソ司祭のもとに行ってもらう。しかしながら、モスコーソ殿は一筋縄ではないお方だ」と、脳裏にその姿を思い描くように、トゥパク・アマルは難しい表情になる。
「マルセラ、そなたは、わたしの書状をモスコーソ司祭に渡すだけでよい。
それ以上、決して、無理をしてはならぬ。
そなたが生きて戻ること、そのことを第一と心得よ」
そう言って、「わかったね」と、さらに念を押すようにマルセラをじっと見た。
「トゥパク・アマル様…」
己の身を真に案ずるトゥパク・アマルの思いが伝わり、マルセラの胸はぐっと熱くなった。
「わかりました」
そう答えながらも、このお方のためであれば、この命、本当に惜しくは無い…――そのような気持ちが激しく込み上げる。
それから、トゥパク・アマルは静かに視線を動かし、その年齢に似合わぬ大人びた鋭利な横顔に、驚きと深く案じる念を色濃く映しているもう一人の凛々しい若者、ロレンソの方を見た。
「ロレンソ殿、そなたの精鋭の兵と共に、クスコの門前までマルセラを護衛してはくれまいか」
トゥパク・アマルの言葉に、ロレンソは深く頭を下げた。
「畏(かしこ)まりましてございます!」
力強く答えて見上げたロレンソの瞳に、トゥパク・アマルは、頼んだぞ、と強く頷き返す。
「出立は、明朝。
それまでに書状を用意いたそう」
そのトゥパク・アマルの言葉で、その深夜の会合はひとまず散会となった。

天幕の外では、星々が、既に夏の星座を描きながら刻一刻と、動きゆく。
足元からは、夏の虫の声がする。
トゥパク・アマルの天幕を去るビルカパサとマルセラを、アンドレスがすかさず追った。
「マルセラ!!」
血相を変えているアンドレスを振り返るマルセラの表情は、もはや、ゆるぎない決意の色である。
ビルカパサも、相変わらず冷静な眼差しでアンドレスを見る。
一方、アンドレスは、強張った表情で、マルセラに詰め寄った。
「マルセラ、これがどれほど危険なことなのかわかっているのか?!
モスコーソ司祭は、キリスト教に何の危害も加えていないトゥパク・アマル様を破門にまでしたお方だ。
俺たちインカに対する憎悪の塊のようなお方だ!
そんな司祭の前に、マルセラ、君、一人が行くなんて!!
それが、どんなに危険なことか、わかっているのか?!
駄目だ!!
こんな無謀なこと、俺は認めない!!
考え直すんだ、マルセラ…俺から、トゥパク・アマル様に、もう一度話をするから、だから…!!」
堰切ったように言いながら、アンドレスは思わず、むせ返る。
しかし、すぐにまた険しい表情で、いっそうマルセラに詰め寄った。
「君の命が…マルセラ…君は、殺されるかもしれないんだぞ!!
トゥパク・アマル様も、今度ばかりは、正気の沙汰とは思えない。
君を一人で行かせるなんて…!
君を行かすくらいならば、本当に、俺が…!!」
アンドレスの言葉に、覚悟を決めたはずの瞳が再び揺れはじめるマルセラの横顔を見て取るなり、ビルカパサが素早く二人の間に割って入る。
「アンドレス様、あなた様が単身クスコなどに行こうものなら、どのような目に合わされるか、火を見るよりも明らか。
あなた様が、トゥパク・アマル様の近しいお血筋であることなど、もはやクスコの役人たちは、とうに調べ上げているはずです。
しかも、あなた様の前線での戦いぶりも、知れ渡っている。
そんなあなた様がむざむざ使者として出向こうものなら、虐殺はもとより、生け捕りにされ、人質にされ、いいように利用されるのが関の山。
そんなことになろうものなら、ここまでトゥパク・アマル様やあなた様が慎重に進めてこられた反乱計画のすべてが水泡に帰すのです」
礼を込めながらも、厳然とした眼差しで語るビルカパサのその声は、冷徹そのものだった。
だが、アンドレスも引き下がらない。
「ビルカパサ殿!
あなたが今、言ったのと、それと同じ危険がマルセラにも起こりえるのです!!
ましてや、マルセラは、女性なのです。
あのような悪鬼のごとくのスペイン人役人たちの中に、マルセラを一人放り込むなど…、どのような酷い目に合わされるか、それこそ想像するだけで身震いが起こります。
俺は、そのようなこと、絶対に容認できません!!
俺から、トゥパク・アマル様に、お考え直しを進言いたします!!」
しかし、ビルカパサは感情を統制し切ったあの眼差しと声で、短く、毅然と応ずる。
「トゥパク・アマル様の決定は絶対です。
それに、もしマルセラがそのような目に合おうとも、あるいは、生きて戻れぬとも、それはマルセラの運命がそこまでであったということ。
その時は、マルセラは、もはや最初からいなかったものと思うしかありませぬ」
「なっ…――!!」
アンドレスは思わず絶句し、だが次の瞬間には、全く無意識のなせる業であったが、本人も止められぬまま、非常に険しい眼でビルカパサを睨みつけていた。
「ビルカパサ殿、それでは、何かあればマルセラを見捨てると?!」
ビルカパサは顔色一つ変えず、「その時は仕方ありませぬ」と、短く答える。
殆ど反射的に、アンドレスの指がビルカパサの襟元に掴みかかった。
「ビルカパサ殿、あなたは…あなたは、なんという冷たいお人だ!!
マルセラは、我々にとって、かけがえのない仲間なのですよ!
ましてや、あなたの姪ではありませんか!!」
既に鍛え抜かれたアンドレスの指は、同様に逞しいビルカパサの首さえもガッチリと締め上げるのに十分だった。
アンドレスの指は、憤りに震えながら、さらにビルカパサの首を締め上げる。
ビルカパサは完全に息の根を止められた状態で、その顔色がたちまち青黒く変異していく。
しかし、ビルカパサはアンドレスに掴みかかられたそのままの体勢で、深く礼を払うように頷き、「アンドレス様、マルセラの身をそこまで案じてくださること、誠にありがたきことに存じます」と、擦れた声で恭しく言う。
すっかり興奮状態にあるアンドレスには読み取れはしなかったが、ビルカパサのその瞳には、全く嫌味な色はなく、むしろ誠実さと感謝の色に溢れていた。
マルセラは予測だにせぬ事態の展開に驚愕しながら、しかし、ともかくビルカパサの顔色の変化にすっかり慌てて、二人の間に入ろうとする。
「アンドレス様、おやめください!!
叔父様、しっかりして!!」
ビルカパサを締め上げるアンドレスの手は固く、マルセラの力では、とてもほどけない。

そこへ走って割って入ってきたのは、アンドレスの朋友、あのロレンソだった。
「アンドレス、何をしている!!
落ち着け!!」
ロレンソはアンドレスの手に己の手を添えると、その冷静な落ち着いた手つきで、ビルカパサを締め上げている友の指を素早くほどいた。
本当に息の止まっていたビルカパサが、その場にむせながら跪く。
ロレンソは、まだ非常に険しい眼のまま興奮のために肩で息を荒げているアンドレスを見据え、諭すような声で言う。
「アンドレス、ビルカパサ殿を殺す気か?!」
そして、まだ目を血走らせている友の顔を、正面から真っ直ぐ見つめた。
「アンドレス、そなたならわかるはずだ。
ビルカパサ殿とて、本心はどれほどご心配されていることか」
ロレンソの言葉に、アンドレスの瞳は、再び、大きく揺れはじめる。
「アンドレス、案ずるな。
マルセラ殿は、わたしがお守りする」
その言葉に、ビルカパサは深く頭を下げた。
アンドレスも、苦しげな眼差しで、改めて朋友を見上げる。
その瞳に、ロレンソは凛々しく微笑み、「案ずるな」と力強く頷き返した。
一方、インカ軍の中枢部でそのようなことが起こっているなど、露ほども知る由のない一介の義勇兵であるコイユールは、その晩もインカ軍本営の一隅に設けられた負傷兵たちの寝所で過ごしていた。
日ごとに増加する負傷兵たちの看病と、そして、痛みを訴える兵たちに、その特有の自然療法を施して苦痛の緩和を図るために、最近では、夜間に自分の寝所に戻る時間もままならぬほどになっていた。
「楽になったようだ」と、少し元気を取り戻した笑顔を見せる負傷兵の傷口に添えていた自分の手をそっと離し、コイユールも静かに微笑む。
「痛みが強くなったら、またいつでもお声をおかけください」
そして、兵にきちんと礼を払い、音を立てぬようにその場を離れた。
テントの隙間から見上げる群青色の夜空に描き出される夏の星座は、既に深夜の位置である。
コイユールは、累々と横たわる負傷兵たちの姿を見渡した。
皆、一応の眠りにつくことができたようで、痛みを訴えている者も今は見られない。
ほっと小さく安堵の溜息をつき、少しだけ仮眠をとるために、同じく負傷兵たちの看護に当たっている女性たちの眠るささやかな臨時の寝所に向かう。
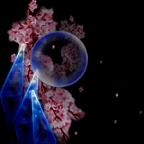 真夜中の初夏の涼風が、彼女の疲れた体をいたわるように優しく吹き抜ける。
真夜中の初夏の涼風が、彼女の疲れた体をいたわるように優しく吹き抜ける。
その時、ふと草陰の方から人の気配を感じ、コイユールは、はたと周囲を見渡した。
少し前方で、黒い大木の陰に溶け込むようにして、立ち竦んでいる者の姿が見える。
コイユールは目をこらした。
「マルセラ?!」
驚いているコイユールの方に、マルセラは「来ちゃった!」と、はにかみながら片手を上げて応じる。
その表情に、コイユールは、マルセラが隠そうとしている不安気な色を瞬時に読み取ってしまう。
「何かあったのね」と、真剣な顔で近づいてくるコイユールに、マルセラは微妙に頷き、「夜が明けたら、クスコに行くことになったんだ。トゥパク・アマル様の使者として」
「え?!」と驚愕して目を見張るコイユールの瞳の中で、「何となく、あんたの顔を見たくなったから…」と、マルセラは笑顔をつくりながらも、物言いたげにじっとコイユールの方を見る。
マルセラの瞳には強い覚悟の色が確かに見えたが、そのもっと奥の方では、本人の意思を超えて、まるで救いを求めているかのような悲壮さがあるのをコイユールは見逃さない。
そのマルセラの瞳の奥で揺れるものを、コイユールは食い入るように覗き込んだ。
マルセラが押し込めようとしている渦巻くような不安と恐怖の念が、コイユールの中に激しく流れこむ。
二人は震える眼差しで、暫し、ただひたすらその目を見つめ合った。
「駄目だね。
やっぱり、あんたの顔を見てしまうと、あんなに張り詰めていた気持ちが緩んでしまう…。
ここに来ちゃいけなかった…」
擦れ声で小さく呟くマルセラを、コイユールはかける言葉もなく、ただ、しっかりとその腕で抱きしめた。
コイユールの腕の中で、平素は男勝りを装うマルセラの細い肩が、明らかに震えている。
極度の心配とせつなさで、コイユールは言葉も出ず、ただもう夢中でその細い肩を抱きしめていた。
マルセラ、マルセラ!!…――と、あまりにも大切な友の名が、コイユールの頭の中で駆け巡る。
いつの間にかその瞳から涙をこぼしているコイユールの腕からそっと離れ、マルセラが、ありがとう、と、そのまだ揺れる瞳で頷く。
それから、「そんなに心配しなくて、大丈夫よ。私はトゥパク・アマル様の書状をお渡しするだけだし、それに、こんなお役目を果たせることを誇りに思っているんだから」と、コイユールを安心させるかのように、そして、自分の心をも確かめるように言う。
コイユールも、涙を落としながらも、深く頷き返した。
「私…本当に、いつも何もできないけれど…でも、祈ってる。
夜が明けたら、明日はマルセラのためだけに、ずっと祈ってるから!」
必死な面持ちで言うコイユールに、「ありがとう!あんたのは、本当に効くものね」と、マルセラはいつもの闊達な笑顔を取り戻し、応じた。
それから、少し間を置き、まじめな顔になって、真っ直ぐにコイユールの顔を覗き込む。
「あのさ…コイユール。
以前、私が、アンドレス様を冷たいお人だと言ったこと、あれは撤回するよ」
そう言うと、マルセラは頬を少し赤らめて、コホンと軽く咳払いをした。
え?…――と、ふいにアンドレスの名が出て、コイユールはまだ涙の滲むその目を瞬かせる。
それから、インカ軍に加わったコイユールに全く声もかけてこないアンドレスのことを、「冷たい」と以前マルセラが言ったことを、思い出した。
マルセラが、何故、前言撤回をしたのかはコイユールには分からなかったけれど、きっとアンドレスとマルセラの間で、彼女の心を溶かす何かがあったのだろうと推察できた。
コイユールは、優しい眼差しで頷いた。

彼女の脳裏にアンドレスの面影がよぎり、再びせつない感情が動く。
「アンドレス」――その名が出るだけで、せつなげに瞳を揺らすコイユールの姿に幾度か触れる中で、今や、マルセラも、コイユールの中にあるアンドレスへの特別な感情を十分に悟っていた。
そんなコイユールの気持ちを察するように、マルセラは心を込めた声で続けた。
「もうずっと前だけど…、コイユール、あんたが義勇兵に加わったことを伝えた時、アンドレス様は本当に嬉しそうにしていたんだよ」
コイユールの目が見開かれる様子に、マルセラは微笑み、しっかりと頷いた。
「だから信じていいと思う。
アンドレス様は、あんたのこと、きっと今も大事に思っているに違いないよ」
「マルセラ…」と、胸が詰まって言葉を続けられずにいるコイユールに、「よおし!何だか、元気出てきたよ!じゃ、朝になったら、しっかり祈っといてね!!」と、そのしなやかな右手を上げると、マルセラは笑顔で踵を返し、トゥパク・アマルの側近たちの天幕の方に戻っていった。
後に残されたコイユールはその場に立ち尽くしたまま、マルセラを深く案じる思いと、アンドレスへの溢れるせつない思いとに憑かれ、そしてまた、一方で、その二人の活躍に胸を熱くもしていた。
そして、心のどこかで、自分の無力さを、ひどくもどかしくも感じていた。
死と背中合わせのギリギリのところで行動し続ける、これほどに大切な者たちのために、一体、自分は何ができているのだろか…――。
何も…、何ひとつ、できてなどいないのだ、と、コイユールの心に乾いた隙間風が吹き抜ける。
悲痛な表情で見上げると、既に夜明けも近いのか、群青色の空が僅かに白みはじめていた。
彼女は小さく溜息をつき、寝所に行くのをやめて、再び負傷兵の待つ治療場へと戻っていった。


